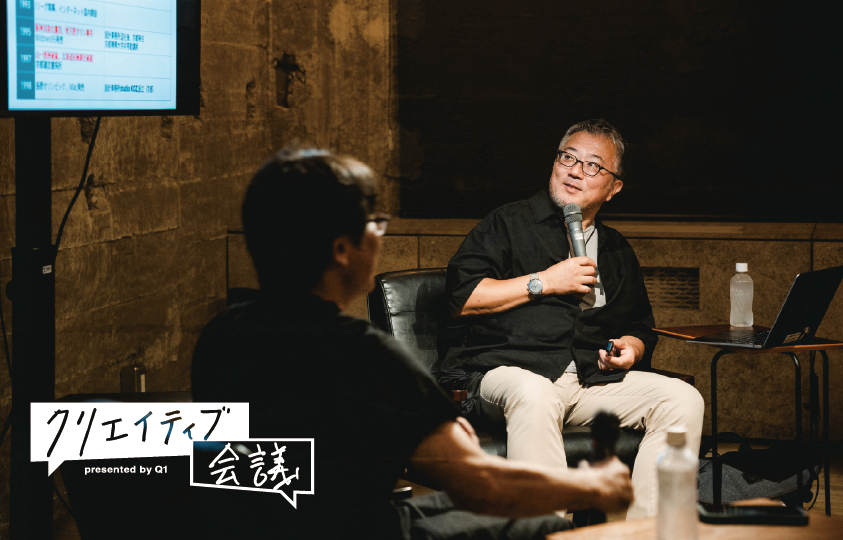やまがたクリエイティブシティセンターQ1オープン後最初のクリエイティブ会議は「地域と人の関係をつくる」と題して、クリエイティブディレクターの清水真介さんをゲストにお迎えします。清水さんは、岩手・盛岡にある合同会社ホームシックデザインの代表として、これまでに様々なデザインワークを手掛けてこられました。その清水さんの多彩な仕事の中から今回は、盛岡市が2018年から開始している「盛岡という星で」プロジェクトにフォーカスしてお話を伺います。
「盛岡という星で」は、盛岡市の「関係人口」に着目したプロジェクトで、移住やU・Iターンという「定住人口」でもなく、観光という「交流人口」でもない、地域との関わりやつながりにフォーカスした取り組みです。関係をつくるという、一見するととても曖昧な目標設定の中で、どのようにプロジェクトを進めているのかを根掘り葉掘り伺いながら、山形でもどのような関係人口が創出できるかをイメージできたらと思っています。
そこに住んではいないが、特定の地域と多様に関わる人のことを指す「関係人口」は、国土交通省調査によると全国に1800万人以上もの人々が存在しており、観光以上・移住未満の第三の人口とも言われています。まちに関係人口が創出されると、どんなことが起こるのか? 地域と人との関係性づくりに関心がある方はぜひご参加ください。
―アイハラケンジ(株式会社Q1取締役・プロデューサー)―
◾️詳細
第12回クリエイティブ会議「地域と人の関係をつくる」
登壇:清水真介(合同会社ホームシックデザイン代表社員)
モデレーター:アイハラケンジ(株式会社Q1取締役・プロデューサー)
開催:令和5年2月26日[日]14:00〜15:30
会場:Q1 イベントスペース[2-C]
主催:山形市、株式会社Q1
企画運営:株式会社Q1
◾️プロフィール
清水真介(しみず・しんすけ)
合同会社ホームシックデザイン代表/プロデューサー/クリエイティブディレクター/プランナー/アートディレクター/デザイン講師
1982年岩手県一関市生まれ。岩手大学教育学部芸術文化課程(視覚伝達デザイン研究室)を卒業後、同大学院に進学。言語情報や視覚情報、素材自体が持つ情報や印刷加工によって素材に起きる現象による情報、などといった各種情報の優位性について興味を持ち、研究と制作を重ねる。大学院に在籍中からhomesickdesignを屋号としフリーランス活動をはじめる。東京と三重での暮らしを経て2010年に盛岡へ帰郷し、正式にデザイン事務所を立ち上げる。東北の作家に焦点を当てた企画展を行うシグアートギャラリー(Cyg art gallery)の運営も行う。 グラフィックデザイナー、アートディレクターとしての役割を経て、現在はクリエイティブディレクターやプロデューサーとして活動中。ブランディングやコンサルティングの視点から様々なデザインやプロジェクトに関わる。2011年より盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校の非常勤講師を務めており教育的な視点でのアプローチも大切にしている。多種多様なクリエイターが力を発揮する環境を盛岡に作りたいという強い気持ちが、経営や活動のモチベーションになっている。
アイハラケンジ(あいはら・けんじ)
アートディレクター、グラフィックデザイナー。1974年東京都生まれ、仙台市育ち。東北芸術工科大学卒業、同大学院修了。主な活動領域はデザインとその周辺。展覧会のキュレーションや展示構成・デザイン、アーティストブックの企画・制作・出版、アーティストマネジメント等の活動も多い。また、厚生労働省「障害者の芸術活動支援モデル事業」への参画をきっかけに、2014年より障害者の芸術活動の調査・発掘、展覧会キュレーション、アートディレクション、デザインなどでも活動している。山形ビエンナーレには過去全ての回に参画。株式会社アイケン代表、halken LLP(ハルケン)共同主宰、inukkuma! LLP(イヌックマ)共同主宰、株式会社Q1 共同創業者/取締役/プロデューサー、コマーシャルギャラリー「famAA」(ファマ)共同オーナー/ディレクター。武蔵野美術大学非常勤講師、専修大学非常勤講師、東北芸術工科大学准教授も務めた。
クリエイティブ会議とは
Q1が目指す「クリエイティブと産業を暮らしで結び、それらを山形の持続可能な社会へ還元する」ための具体的な方法論や事業の可能性をテーマに、先進的な活躍をされているクリエイター/アーティスト等のゲストとQ1プロデューサー/ディレクター陣がディスカッションする公開型の企画会議です。
Q1チャンネルとは
Q1チャンネルは、株式会社Q1が運営するYouTubeチャンネルです。ゲストを招いたトークセッションや、様々なQ1のプロジェクトなど、「山形×産業」の可能性を探るコンテンツを発信していきます。