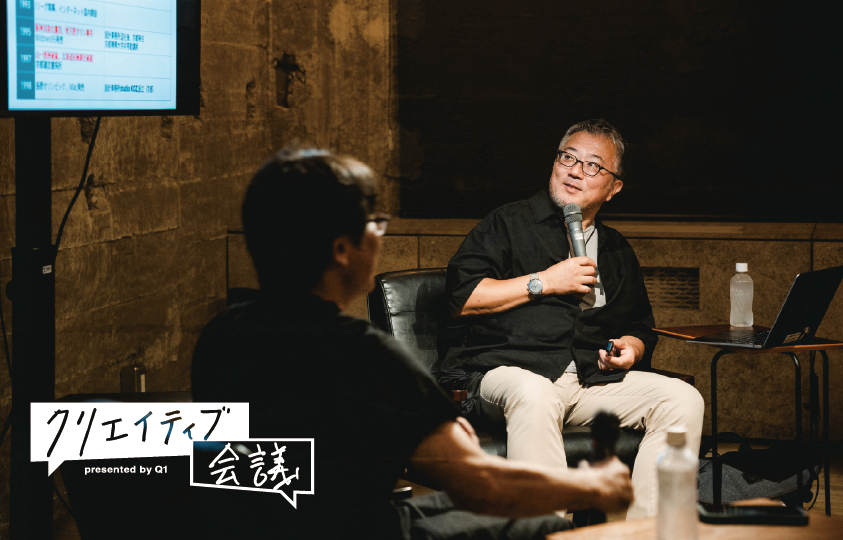第16回クリエイティブ会議「食とデザイン 未来のヒント」レポート
2024年11月23日、やまがたクリエイティブシティセンターQ1にて「第16回クリエイティブ会議」が開催されました。ゲストは、庄内・山形そして日本を代表するイタリア料理人、奥田政行シェフ。モデレーターを務めたのは、Q1ディレクターでもある東北芸術工科大学の中山ダイスケ学長です。

「クリエイティブ会議」とは、まちのクリエイティブと産業とをどうやって結びつけていけるのか、そして持続可能な地域社会づくりにどのように繋げていけるのか、その具体的な方法論や可能性を探ることを目的として、先進的な活躍をされているクリエイターとQ1ディレクター陣がディスカッションする、公開企画会議のようなもの。
16回目となる今回のテーマは「食とデザイン 未来のヒント」。ゲストの奥田政行さんは、山形県鶴岡市の地場イタリアンレストラン「アル・ケッチァーノ」オーナーシェフであり、その後全国さまざまな場所に誕生することとなる地産地消レストランの先駆者。世界に名を馳せる料理人であり、自身のお店だけでなく地域全体を元気にしてしまう飲食店経営のスペシャリストであり。さらにはいくつものお店や商品のプロデューサーでもあり……という、常人ならざる精力的な活躍をされています。

さて、この会議では、そんな奥田シェフと中山学長とのあいだで約1時間に渡ってトークが繰りひろげられました。その内容はイタリア料理という枠をはるかに超え、話題はあっちへこっちへそっちへとさまざまな方向に飛び跳ねつづけます。
父親の大きな借金を背負った話。資金がないなかで編み出された経営的工夫。生産者の方たちとともに編みだした物々交換の経済。お店の若い男女スタッフをくっつける方法。歴史に学び、未来を予測する話。料理修行を2年でマスターする方法。自分にとっての約束の地とはどこかという話。イタリアンとは素材第一の料理であるという定義。素材から見極める調理の熱媒体のこと。タンパク質とアミノ酸についての話題。3つの素材から創造するおいしさの黄金法則について。生産者の年収を増やすためにやれること。そして、おそらく世界一食材のバリエーションに恵まれた山形、などなど……。その話題の豊富さ、考えかたの独特さ、理論の独自性には圧倒されるものがありました。

ここでは、そうした数々の話題のなかから、いち参加者として特に強い印象を受けたポイントについて感想を述べます。
調理の発想に至る素材分析の力
奥田シェフから、食材というのはすべて地球上の生きものであること、そして料理とは、その生きものが生きているときには体験したことのなかった熱を、水で(茹でる)、油で(フリットにする)、空気で(ローストする)などして加えるものである、というユニークな定義づけの紹介がありました。それらの熱媒体のどれを選ぶかというと、それは素材を見て、含まれる水分量や香りや可食部の大きさといった性質から適切な熱媒体を決める、というようなお話です。
完成された料理を先に志向するのではなく、まずは目の前にある食材の性格をしっかりと見極めることが大切だということ。そこで重要になるのは素材分析の鋭さでしょう。奥田シェフは地元の野山を歩き回りながら野草や山菜を摘んでは食べて味を確かめていたというエピソードが有名ですが、そうした食材の一つひとつをしっかり見極め、香りを嗅ぎ分け、味わうということを、まるで野生の獣のように研ぎ澄まされた感覚をもって経験し、身につけていったのではないでしょうか。その素材分析ができてはじめて料理が導かれていくというそのベクトルのユニークさと、それを支える野生的な感覚に驚きを感じました。
料理を、言葉や数字や音符に変換する
奥田シェフと中山学長おふたりの話しぶりから終始滲み出ていたのが、知識量の凄まじさです。フレンチ、イタリアン、洋菓子といったカテゴリーのそれぞれをいずれも2年間の修行でマスターしていったという奥田シェフは、このトークのなかで、自身で描いた各料理の体系図を紹介されていました。料理をメニューの名前で覚えるのではなく、そもそもどんな料理なのか定義づけし、どのような構成要素や組み立てによって成立しているのか体系立てて理解し、図や言葉などに変換して明確化し、そして基本的な技術を覚える、ということの重要性が語られていたようです。それは「料理は見て覚えろ」というセリフが常套句となっている業界にあって特異な態度であり、アンチテーゼかもしれません。
料理は食べてしまえば残らないものである一方で、おいしさの記憶としては後々まで残るもの、という話題も興味深いものでした。特に、音楽の楽譜のように料理を音符にすることができれば遠くに飛ばすことも可能になる、というエピソードが気になりました。いったい、料理の「音符」とはなんなのか。いわゆるレシピとは違うのか、興味をそそられました。奥田シェフはその音符の発明により、自身の元で技術を学んだ若い料理人に新しいお店に飛んでもらい、その音符を送り込めば料理を奏でてもらうことができるというやり方によって、遠くの街にプロデュース店をひらくことができるようになった、というようなことをおっしゃっていました。
料理という、感性に依るところが大きいような仕事を、積極的に言葉に変換すること、突き詰めて考えること、定義すること、図表にすること、音符に変えること、そしてトークすること……。そのアウトプットする創造力の大きさを感じました。
繁盛店をつくり、食の街をつくる
料理の話をしているのにも関わらず、すぐに料理の領域を超えていくところも面白く感じました。
たとえば、100人の村に10軒のイタリアンがあればお客は10人しか来ない、けれど、100人の街で誰もやっていないたった1軒だけの店をやれば、20%の人が食べたいと思っただけで繁盛店になれる、という話題。これはブルーオーシャン戦略であり経営論でしょう。また、店を繁盛店にするためには街づくりからやらなければならないという話や、プロデュース店を増やしていくことによって生産者の年収アップや後継者づくりに寄与することができるという話も、料理人の枠を超えたスケールを感じさせました。
おいしい料理をつくることと、自分の店を繁盛させること、生産者を支援すること、若い人を育てること、まちの未来をもっと良くしていくことが矛盾なく自然に繋がり、重なっているのです。
食のクリエイションがひらく地域の未来
昨今、東京を中心とした都会では、「山形」というと「おいしい酒、おいしい米、おいしい土地」というような「おいしいイメージ」が定着しつつある、という話題もありました。しかし、そうした状況にもかかわらず、山形に暮らしている地元の人たちは、「置賜が、村山が、最上が、庄内が」と自分たちの小さなエリアの縛りばかり意識していたり、こだわっていたり、「山形なんてまだまだ」と勝手に思い込んでいるフシがあって、せっかくのチャンスなのに残念、というような指摘です。
奥田シェフは、山形は「おそらく世界一の、食材のバリエーションの豊かさに恵まれている」ということをおっしゃっていました。そして「そのことに誰も気づいていない」とも。中山学長は、この山形は「おいしい街」としてのアイデンディティを創出できる可能性が十分にありうるし、サンセバスチャンのように世界的な食の都のようなまちになれる可能性も十分ありうるのだ、というようなこともおっしゃっていました。
食をクリエイションすることは、食材を発見していくことでもあり、そこにある水や土や歴史や文化そして風土といったさまざまな物語を学び直し、紡ぎ出すことでもあります。また、食の繁盛店をつくりだすということは、街のにぎわいを生み、風景を変え、人の動きを変化させ、農業や観光に好影響をもたらし、新しい経済が生まれ、新しい循環をもたらす可能性をつくりだすことでもあります。
今回のこのクリエイティブ会議から見えてきたものは、食のクリエイションという切り口から見たとき、この山形という街のもつポテンシャルはとても大きい、ということを再発見する必要がある、ということではなかったでしょうか。そして、その先に街の未来がひらかれる可能性があるということであり、ここに生きる私たち一人ひとりがそのことを信じられるのかが問われているのでは、という気がしました。
終わり
クリエイティブ会議とは
Q1が目指す「クリエイティブと産業を暮らしで結び、 それらを山形の持続可能な社会へ還元する」ための具体的な方法論や事業の可能性をテーマに、 先進的な活躍をされているクリエイター/アーティスト等のゲストとQ1プロデューサー/ディレクター陣がディスカッションする公開型の企画会議です。
Q1チャンネルとは
Q1チャンネルは、 株式会社Q1が運営するYouTubeチャンネルです。 ゲストを招いたトークセッションや、 様々なQ1のプロジェクトなど、 「山形×産業」の可能性を探るコンテンツを発信していきます。
Text: 那須ミノル
real local山形ライター。
https://www.reallocal.jp/yamagata