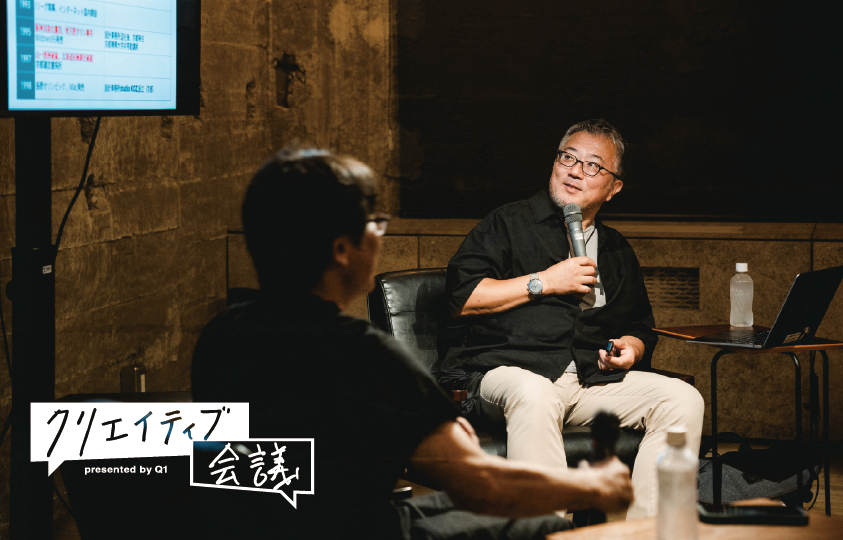地方都市でアーティストやデザイナーとして生きていきたいと思ったことはありませんか?
豊かな自然環境、穏やかに流れる時間、あたたかい人々…。そのような環境の中で生活し、地に足のついたアートやデザインを生み出すこと。もしかするとそれは、これからの時代の理想の生き方=生業の一つかもしれません。今回は、そのような「生業」の実践場としてQ1がどのように機能していくのか?そのアイデアや可能性について語り合います。
深井は、地場産業を用いて魅力的なプロダクトを開発し、発信している実例を挙げ、すでに動き出した平清水焼青龍窯とのプロダクトを紹介しつつ、山形の地場産業におけるプロダクト開発の可能性を語ります。
アイハラは、2019年下半期に関西で開催された東北と山形のグラフィックデザイナーを紹介する企画展の紹介から、地方デザイナーの生業(なりわい)とその独自性について語ります。
◾️詳細
第10回クリエイティブ会議「地方都市・山形でアートやデザインを生業(なりわい)にするためには?」
登壇:深井聡一郎(株式会社Q1取締役・ディレクター)、アイハラケンジ(株式会社Q1取締役・プロデューサー)
モデレーター:馬場正尊(株式会社Q1代表取締役)
主催:山形市、株式会社Q1
企画運営:株式会社Q1
◾️プロフィール
深井聡一郎(ふかい・そういちろう)
1973年 東京都出身。1999武蔵野美術大学修士課程造形研究科(彫刻)修了。修士。2002~2003年文化庁在外派遣研修員として英国に滞在。現在、東北芸術工科大学教授・研究科長、やまがたクリエイティブシティーセンターQ1ディレクター、famAA共同オーナー、彫刻家。陶を素材に彫刻を作っている。主な個展に、INAXライブミュージアム、ガレリアキマイラ、Art Center Ongoing 、新宿眼科画廊、ギャラリーなつかなど。 第9回岡本太郎記念現代芸術大賞(TARO賞)展 ・川崎市岡本太郎美術館、DOMANI明日展2010 ・国立新美術館。SCREWDRIVERメンバー。
アイハラケンジ(あいはら・けんじ)
アートディレクター、グラフィックデザイナー。1974年東京都生まれ、仙台市育ち。東北芸術工科大学卒業、同大学院修了。主な活動領域はデザインとその周辺。展覧会のキュレーションや展示構成・デザイン、アーティストブックの企画・制作・出版、アーティストマネジメント等の活動も多い。また、厚生労働省「障害者の芸術活動支援モデル事業」への参画をきっかけに、2014年より障害者の芸術活動の調査・発掘、展覧会キュレーション、アートディレクション、デザインなどでも活動している。山形ビエンナーレには過去全ての回に参画。株式会社アイケン代表、halken LLP(ハルケン)共同主宰、inukkuma! LLP(イヌックマ)共同主宰、株式会社Q1 共同創業者/取締役/プロデューサー、コマーシャルギャラリー「famAA」(ファマ)共同オーナー/ディレクター。武蔵野美術大学非常勤講師、専修大学非常勤講師、東北芸術工科大学准教授も務めた。
馬場正尊(ばば・まさたか)
建築家/株式会社Q1代表取締役
株式会社Q1代表取締役/Open A代表/東北芸術工科大学教授/建築家。1968年佐賀県生まれ。早稲田大学大学院博士課程建築学専攻単位取得満期退学。修士。博報堂、雑誌『A』編集長を経て、2003年に(株)OpenAを設立。同時期に「東京R不動産」を始める。建築設計・リノベーション(建築の再生)を専門とする。主な作品に、「観月橋団地再生」(2012年)、「Under Construction」(2017年)、「旧那古野小学校施設活用事業」(2019年)など。2015年より公共空間のマッチング事業『公共R不動産』立ち上げ。2017年より沼津市都市公園内の宿泊施設『INN THE PARK』を運営。近著に『民間主導・行政支援の公民連携の教科書』(学芸出版、2019、共著)、『テンポラリーアーキテクチャー:仮設建築と社会実験』(学芸出版、2020、共著)など。
クリエイティブ会議とは
Q1が目指す「クリエイティブと産業を暮らしで結び、それらを山形の持続可能な社会へ還元する」ための具体的な方法論や事業の可能性をテーマに、先進的な活躍をされているクリエイター/アーティスト等のゲストとQ1プロデューサー/ディレクター陣がディスカッションする公開型の企画会議です。
Q1チャンネルとは
Q1チャンネルは、株式会社Q1が運営するYouTubeチャンネルです。ゲストを招いたトークセッションや、様々なQ1のプロジェクトなど、「山形×産業」の可能性を探るコンテンツを発信していきます。